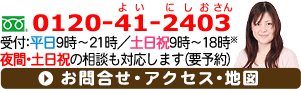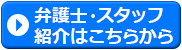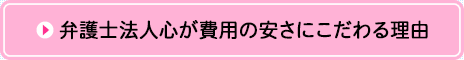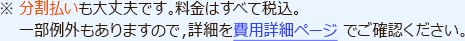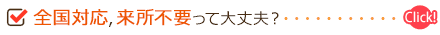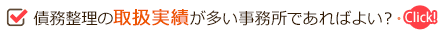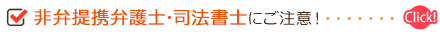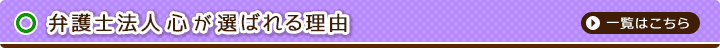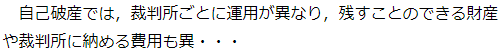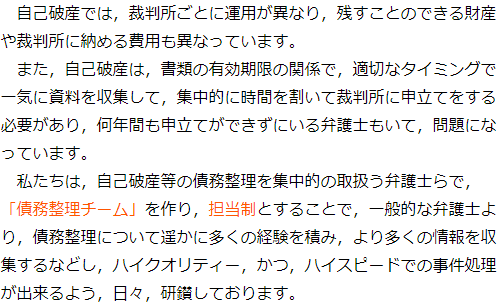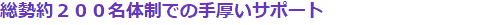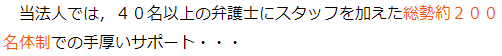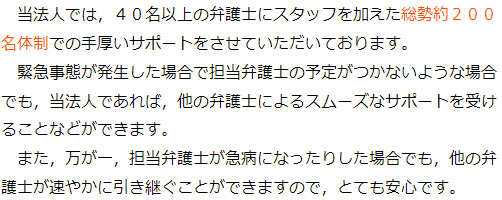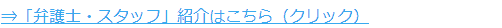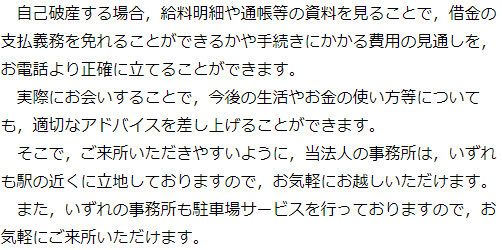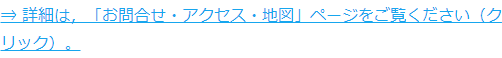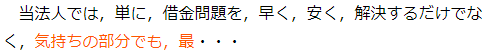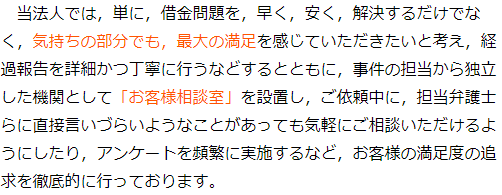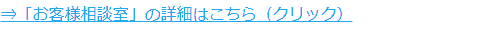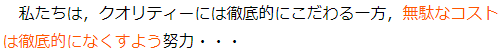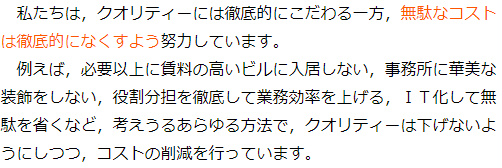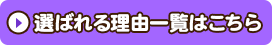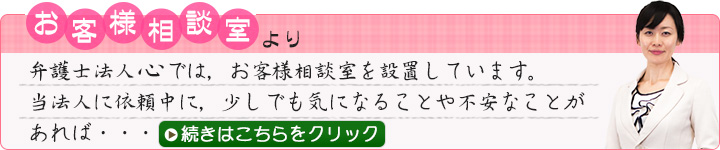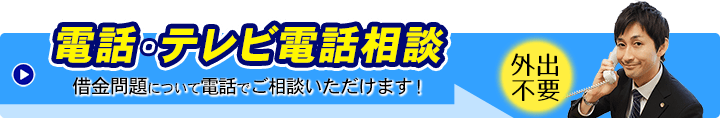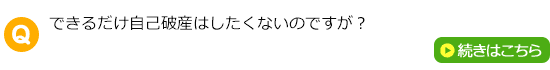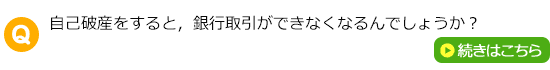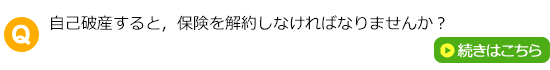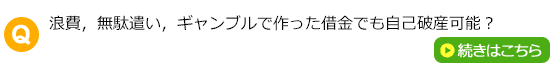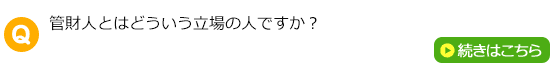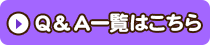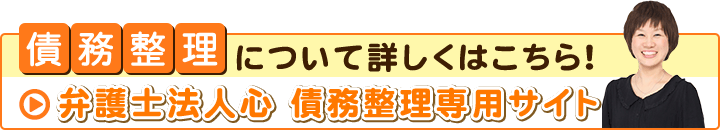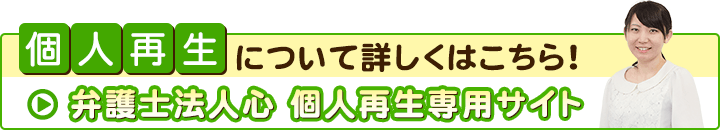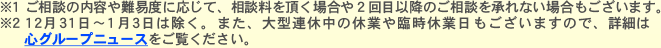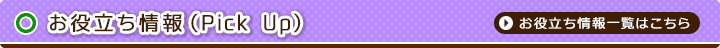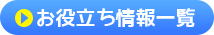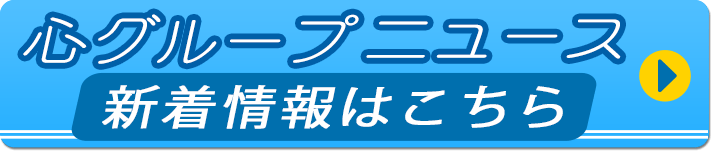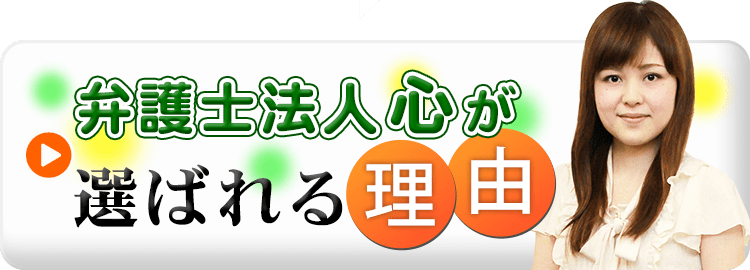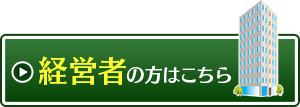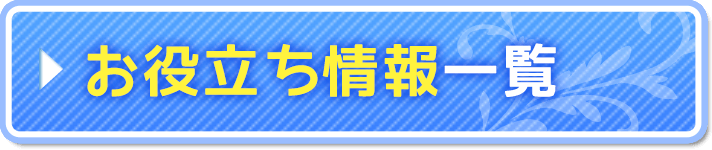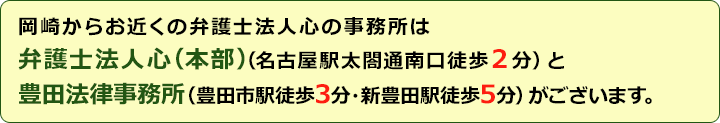
岡崎からも便利な立地
電車でお越しいただきやすい駅近くの立地ですので,自己破産を検討されている方はまずはお気軽に当法人までご連絡ください。
自己破産をしても残せる財産について
1 自由財産について

自己破産は、支払が困難になった場合に、財産を売却する等してお金に換えて債権者に分配し、それでも残ってしまった債務の支払義務を免除する手続きです。
ただし、本当に財産をすべて債権者への支払いに充ててしまうと、次の日からの生活にも困ることになります。
そのため、破産をした場合でも、一定の範囲の財産は手元に残すことができるようになっています。
これを「自由財産」といいます。
2 自由財産の拡張
現金については、自由財産の範囲は99万円までとされています。
また、現金以外の財産についても、必要が認められれば自由財産とすることが認められています。
これを自由財産の拡張といいます。
現金の自由財産の範囲が99万円であることから、現金も含めて99万円の範囲であれば、他の財産についても自由財産の拡張が認められることが多いです。
3 99万円を超える自由財産の拡張
99万円の範囲を超える場合でも、自由財産の拡張が認められることがあります。
個別の事情を考慮した上で、99万円を超える財産を残すことが、破産者の経済的更生に必要不可欠と認められるような場合には、99万円を超える部分についても自由財産の拡張が認められる場合もあります。
具体的には、「破産者が寝たきりの入院中で社会復帰が困難な場合に医療費等の支払いのため」というケースや、「介護のため就労困難な場合に今後の生活費に充てるため」等の必要性が認められた場合に、99万円を超える財産についても自由財産の拡張が認められています。
4 自己破産のご相談は当法人まで
しかし、上記のとおり自己破産を行っても生活に必要な財産は残すことができるので、今後の生活ができなくなることはありません。
むしろ、自己破産等の手続きを行わず借金をそのままにしてしまいますと、返済が滞ってしまった際に給与の差し押さえを受ける等して、より生活が苦しくなってしまうおそれがあります。
そうなる前に、自己破産を視野に入れつつ早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当法人では、自己破産の相談については、原則相談料無料で承っています。
岡崎にお住まいで毎月の返済にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
自己破産における同時廃止と管財事件
1 管財事件

破産しても残すことが認められた財産(自由財産)を超える財産がある場合には、管財事件という手続きになります。
管財事件においては、「破産管財人」と呼ばれる人物が破産者と債権者の間に入って、破産者の財産の監理・売却等を行います。
破産管財人は裁判所によって選任されますが、多くの場合、弁護士が選ばれることになります。
また、財産等がなかったとしても、免責不許可事由がある場合には、破産管財人が選任され、免責を許可すべきどうかの調査を行うことが多いです。
免責不許可事由がある場合には、裁判所は借金等の支払義務を免除しないとすることができると定められていますが、実際は絶対に支払義務が免除されないわけではなく、破産管財人の意見を踏まえた上で、裁判所が免責を許可することもあります。
2 同時廃止
それ以外の場合、すなわち破産しても残すことが認められた財産しかないことが明らかであり、かつ、免責不許可事由がない場合には、破産管財人を選任する必要がありません。
そのため、管財人が選任されない同時廃止という手続きが取られることがあります。
3 管財事件と同時廃止の違い
管財事件になると、管財人に選任される弁護士の報酬を負担しなければならないため、同時廃止の場合と比べ20万円から60万円の費用がかかることになります。
また、同時廃止であれば裁判所に行かずに済むことも多いのですが、管財事件になると裁判所や管財人の事務所に行くことが求められ、さらに、管財人の調査等に協力することも必要になります。
したがって、管財事件になると、同時廃止の場合と比べて、金銭の面でも時間の面でも負担が多くなります。
そのため、なるべく同時廃止の方向で進めていきたいと思われる方が多いと思いますが、同時廃止か管財事件の基準は裁判所ごとに異なります。
同時廃止になるか管財事件になるかについては、地元の経験豊富な弁護士でなければ分からないことが多いですので、まずは相談してみることをおすすめします。
自己破産による家族への影響
1 家具等について

自己破産とは、簡単に言うと、財産を売却し、それを債権者に平等に分配し、その上で、残ってしまった債務の支払義務を免除するという手続きです。
破産すると家具や家電などを取られてしまい、家族が生活できなくなってしまうと考えている方もいらっしゃいます。
しかし、これは誤解です。
仮に、破産をしたとしても、生活に必要な家具や家電等については手元に残すことができます。
パソコンやテレビ等についても、高額なものでなければ、そのまま手元に置いておくことができます。
その他の生活に必要な財産、例えば自動車等についても、年式が古く、売却しても大した金額にならないようなものは残すことができます。
2 住居について
住居についても、賃貸なら大半の場合はそのまま住み続けることができます。
ただ、家賃の支払が遅れているような場合には注意が必要です。
また、持ち家がある場合には、こちらは売却して、売却代金を債権者の配当に充てなければならないため、退去することが必要になります。
したがって、住居については、賃貸で家賃の支払も遅れていなければ問題はないのですが、家賃の支払が遅れていたり、持ち家だったりする場合には、退去しなければならないこともあります。
3 信用情報
自己破産を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
そのため、新しくクレジットカードやローンの申し込みをしても、大半の場合、審査に通らなくなってしまいます。
ただ、信用情報は個人ごとに管理されているため、原則としてご家族の信用に影響を与えることはありません。
また、自己破産後5~7年程度が経過し、信用情報の登録が削除されれば、再度クレジットカードの作成やローンの申し込みもできるようになる可能性があります。
4 戸籍
自己破産をしても、そのことが戸籍に記載されるということはありません。
そのため、この点から、ご家族の結婚や就職に影響が出るということはありません。
5 家族への影響について
以上のとおり、自己破産をしたとしても、ご家族への影響は限定的なものにとどまります。
ただ、何事にも例外はありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
破産しても支払いを免れない債務
1 非免責債権

自己破産をすると、債務の多くが免責され、支払いの義務が無くなります。
しかし、自己破産をしても免責されない「非免責債権」もあります。
2 税金や年金等
まず、一定の範囲の税金などが該当する財団債権については免責許可の効果は及ばないことになります。
つまり、住民税や国民年金、国民健康保険等の滞納については、そのまま支払い義務が残ることになります。
3 一部の損害賠償請求権
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権についても、原則として支払い義務が残ります。
民法などでは、「悪意」とは、単に知っていること、故意があることを表すことが多いですが、ここでは単に故意があるだけではなく、他人を害する積極的な意欲、すなわち「害意」を意味すると考えられています。
生命、身体については、他人を害する積極的な意欲までない場合でも保護するため、「故意または重大な過失」についても非免責債権とされています。
4 婚姻費用、養育費などの支払債務
婚姻費用、養育費の支払債務についても非免責債権となっています。
そのため、婚姻費用、養育費の滞納分については、自己破産を行ったとしても支払い義務を免れないことになります。
また、破産手続開始後に発生する婚姻費用、養育費については、破産手続き開始後に発生した債務となりますので、免責の対象外となります。
そのため、婚姻費用、養育費については原則として一切免責されないことになります。
5 弁護士にご相談ください
非免責債権としては、他にも 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金などの請求権などがあります。
ご自身が抱えている債務の中で、どれが免責の対象になり、どれが免責の対象とならないのか、正確な判断をお求めの方は弁護士にご相談ください。
また、非免責債権が大部分を占めるような場合でも、破産の手続きをとる意味があることもありますので、そのような場合も、まずは一度弁護士にご相談ください。
当法人では、自己破産の相談について原則無料で承っています。
岡崎周辺にお住まいで借金の支払いにお困りの方は、当法人にご相談ください。
自己破産のデメリット
1 自己破産のデメリットについて

自己破産というと、デメリットの大きな手続きであると思われている方が多いと感じます。
実際は、人によってはほとんどデメリットがない場合もあります。
自己破産の代表的なデメリットは、以下のとおりです。
2 財産の処分
自己破産は、財産を処分して、それを債権者への支払いに充てるかわりに、残った借金の支払い義務については 免除(免責)するという手続きです。
そのため、自宅や車のような、手元にある高額な財産については、処分しなければならない場合がほとんどです。
ただし、すべての財産を処分しなければならないわけではなく、生活に必要な家財や一定額の範囲の現金・預金等については残せます。
また、管財人がつくことになりますが、99万円までについては自由財産として残せることが多いですし、場合によってはそれ以上の部分についても残せることがあります。
3 債権者への支払い
自己破産においては、債権者間の平等が重視されます。
そのため、破産はするけれど、お世話になった親戚や勤務先には返済を続けたいということは、基本的に許されません。
債権者はすべて裁判所に報告する必要がありますし、破産手続き中は一切支払いをすることはできないというルールになっています。
ただし、破産手続後に生活を再建してからの支払いまでは、禁じられていません。
4 資格制限
破産をしますと、資格や職業によっては制限をうけることがあります。
主に、他人の財産を扱ったり、管理したりする職業が、制限を受けることが多いです。
そのため、そのような資格や職業につかれている場合には、破産される前に制限を受けないか確認する必要があります。
5 その他
⑴ 官報
破産をすると、その旨を官報に記載されることになります。
ただし、官報を確認する人は非常に稀かと思います。
⑵ 破産者名簿
破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
破産手続開始決定が出たものの、免責を受けられなかった場合は、本籍地の市区町村役場の破産者名簿に登録され、同役場発行の身分証明書には記載されることになりますが、身分証明書を提出しなければならないことはほとんどありません。
⑶ ブラックリスト
破産をすると、その情報が金融機関等が利用している信用情報機関に登録されます。
登録されている期間は、借入れやクレジットカードの新規作成、ローンの利用等ができなくなる可能性があります。
6 自己破産をお考えの方は一度弁護士にご相談ください
自己破産の代表的なデメリットは上記のとおりですが、デメリット以上に、支払い義務がなくなるというメリットの方が大きい場合も多々あります。
一人一人状況が異なるかと思いますので、ご自身が自己破産を行った場合の見通しやメリット・デメリット等を知りたいという方は、一度弁護士にご相談ください。